どうも。
日々「犬」のことを考えている武雄市の黒岩整体院・院長の黒岩です。
すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが私はある病に侵されており
30年以上に及ぶ闘病生活が続いております。
普段は大丈夫ですが、研修などで上京した際ふいに発作が起こる時があります。
薬(犬)を服用(触る)すると治まりますが
厄介な病(突発性犬触りたくなる病)であります。
さて、今回は犬(飼い犬)についての論文のご紹介です。
■イヌはどうやって人間の最良の友となったのか?
イヌを人間の最良の友としている遺伝子が最近の研究の進歩で明らかになりつつある。米ミシガン大学の研究グループによる新たな研究で、現代のイヌと古代のイヌ、オオカミのDNAを比較した結果、現代のイヌと古代のイヌのDNAには一致しない部分がみられたという。研究の詳細は「BMC Biology」6月28日オンライン版に掲載された。
論文の筆頭著者で同大学のAmanda Pendleton氏によると、世界のイヌの約4分の3を占める“野犬(village dog)”は、約300年前に現れた人間に飼い慣らされた“飼い犬(breed dog)”とは違って人間の生活圏で食べ物を探し、自由に交尾して生きているという。同氏らは、この野犬の遺伝子をオオカミのものと比較することで、イヌが人間に飼い慣らされていく過程で遺伝子に起こった変化を探索する研究を行った。
Pendleton氏らは、世界中に分布する43種の野犬と10種のオオカミについて、一塩基多型(SNP)の全ゲノム解析を実施。その結果、イヌの脳機能や発達、行動に影響を及ぼす246カ所の候補遺伝子領域を同定した。
ここで同定された遺伝子領域の多くは、初期発生過程で一時的に現れ、骨や軟骨細胞、神経細胞、色素細胞などさまざまな細胞種に分化する神経堤細胞が発生・分化するときに活性化されるものであった。このうち「RAI1」遺伝子の変異から、飼い犬が夜行性のオオカミとは違って、日中に起きて活動している理由を説明できる可能性があると、研究グループは指摘している。
Pendleton氏は「今回の結果から、これまで数々の研究で発見された遺伝子は、“イヌという種である”というよりも“飼い犬である”ことに関連するものだと確証した。飼い犬のDNAには、世界中のイヌにみられるDNAの遺伝的な多様性は認められなかった」と話している。
また、Pendleton氏らは、この研究結果は、家畜化された動物にはさまざまな共通点があるとする「家畜化の神経堤細胞仮説」を支持するものだとしている。「この仮説は、人間に飼い慣らされた動物に共通して認められる垂れた耳やあごの変化、色、従順な行動などの表現型が、神経堤細胞の発生中に特定の細胞に作用する遺伝的変異により説明し得るというもの。この細胞は成体のあらゆる組織の形成に関与し、極めて重要なものだ」と同氏は説明している。
さらに、今回の研究で同定されたRAI1以外の遺伝子は、神経堤細胞の発生異常を原因とする特徴的な顔貌といったヒトの先天性症候群と共通していることも明らかになった。論文の最終著者である同大学のJeffrey Kidd氏は「人間とイヌの類似性を明らかにした点でこの研究の意義は大きい」と強調。「何千年もの間、人間によって選択されてきたこれらの遺伝的な変化から、あらゆる脊椎動物の神経堤細胞本来の機能と遺伝子発現の制御機構を解明していきたい」と話している。
原著論文はこちら
Pendleton AL, et al. BMC Biol. 2018 Jun 28. [Epub ahead of print]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29950181
人間と犬(飼い犬)は神経堤細胞など類似性があるようです。
今後、神経堤細胞本来の機能と遺伝子発現の制御機構が解明されていくと面白いですね。


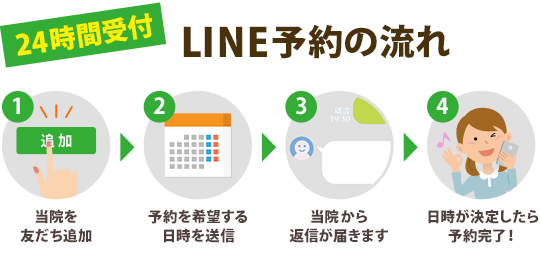
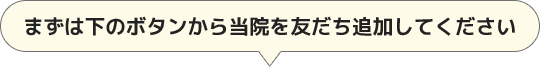


お電話ありがとうございます、
黒岩整体院でございます。